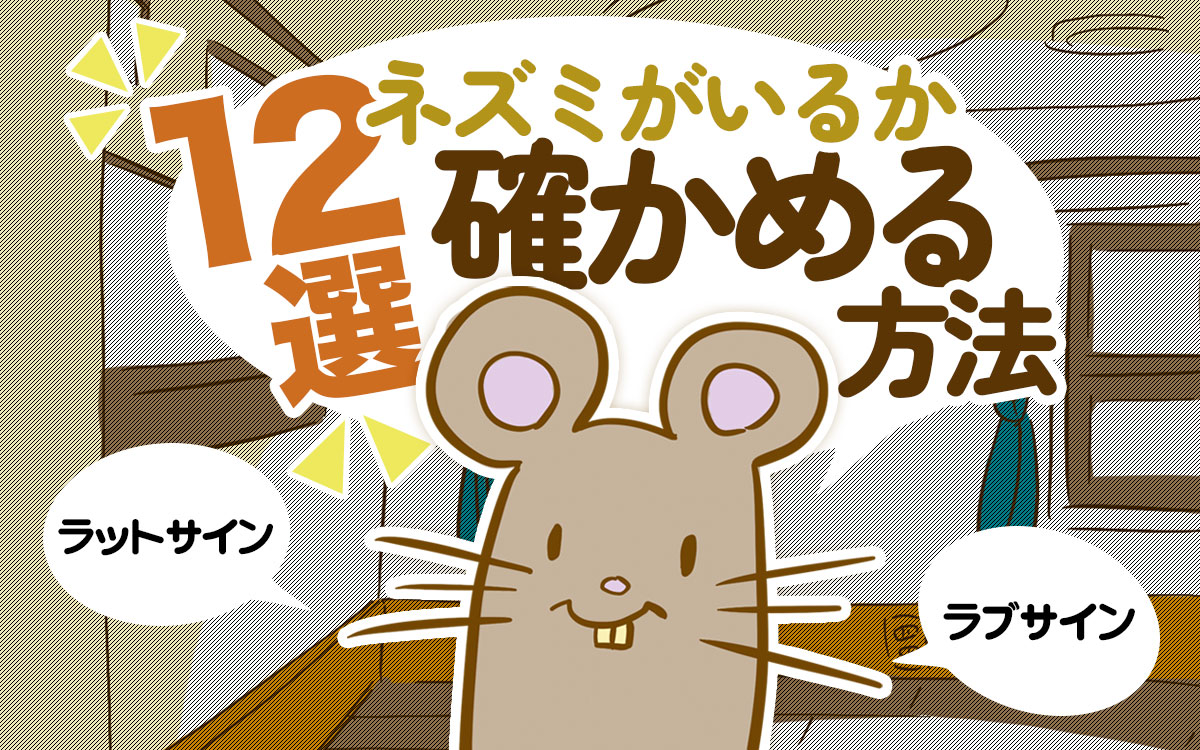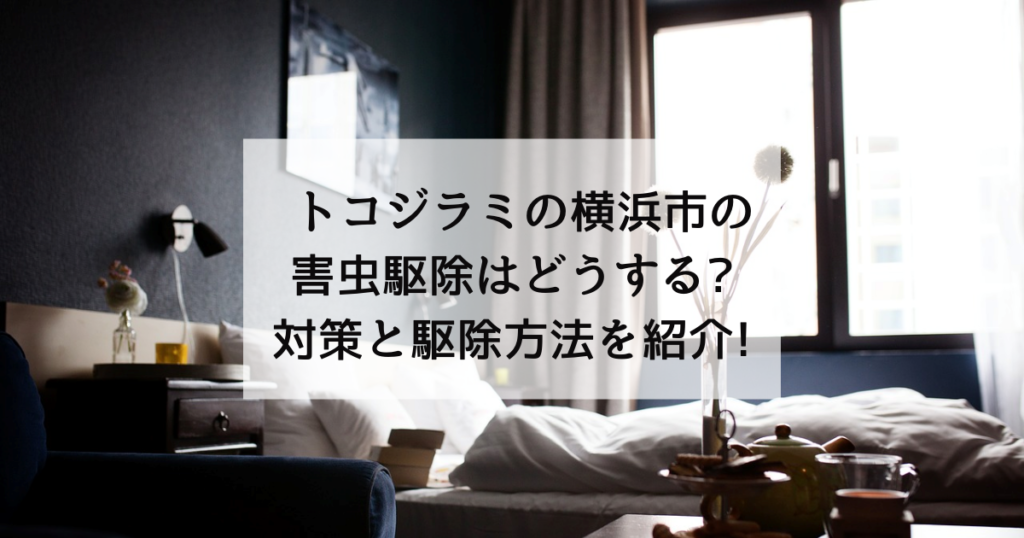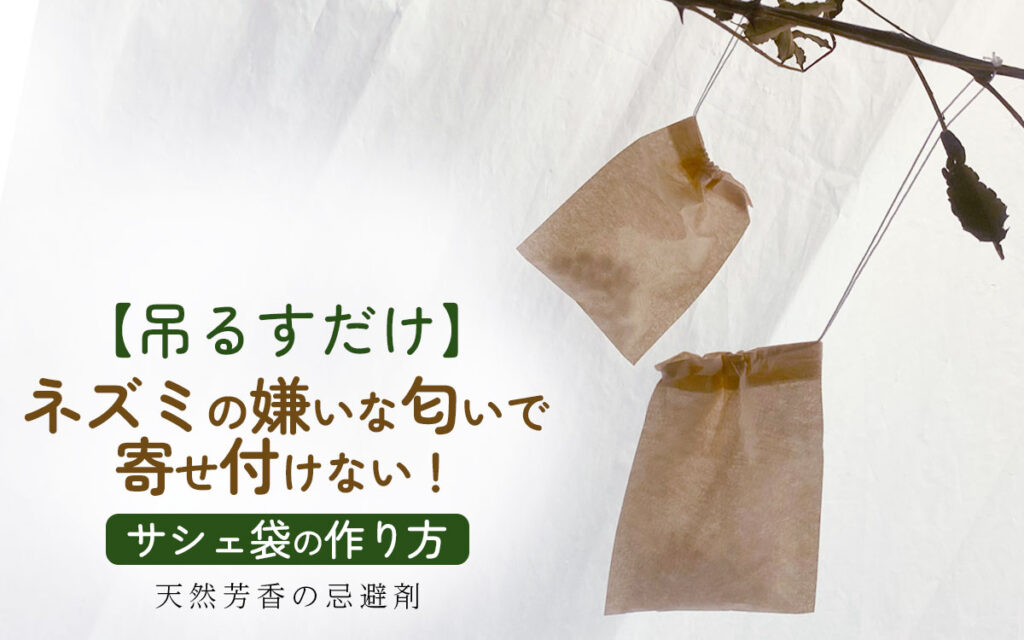こんにちは、プロープル広報のkikuです。
ネズミは臆病で、人前に姿を見せることはあまりありません。
年間500件以上のネズミ相談を受ける弊社でも、相談者の多くはネズミの姿を直接見たことがなく、匂いや物音、フンなどの痕跡から「ネズミがいるかも?」と気づき、調査すると、天井裏や壁の中に巣や大量のフンが確認されることがほとんどです。
ネズミは人目につかない場所で活動し、できるだけ気配を悟られないように行動するため、姿を見せることはめったにありません。
それほど警戒心が強く、慎重に行動する動物です。
しかし、そんなネズミが部屋に現れると、思わず慌てて対処したくなりますよね。
ところが、その対処法が外から虫を呼んでしまう原因になることも……。
今日のテーマは、『部屋にネズミが出た理由』と『虫を呼んでしまう?ネズミの対処法』を解説します。
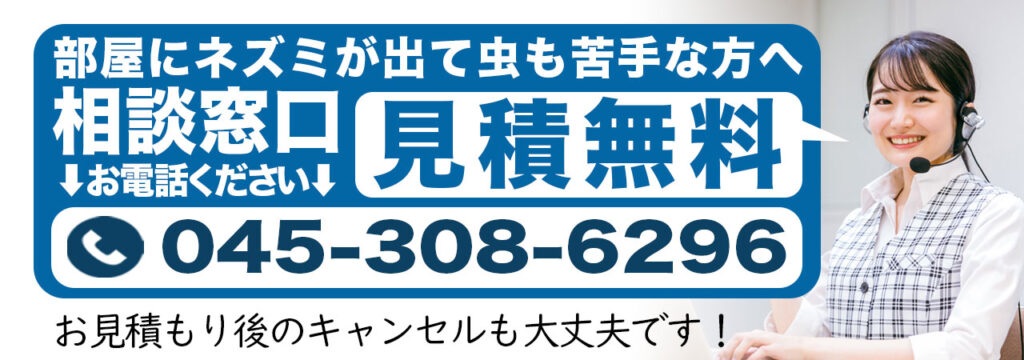
『部屋にネズミが出た理由』とは

ネズミは夜行性の動物です。そのネズミが部屋に出た時間帯でネズミが出た理由を推測してみましょう。
朝にネズミが部屋に出た場合
通常は夜間に活動するネズミですが、状況によっては早朝に目撃されることもあります。
朝にネズミが出る理由とは:環境の変化やストレスが影響しているから。
ネズミは絶えず食べる必要があり、天敵(アライグマ、ハクビシン、ヘビなど)の存在によって夜間に食べ物を確保できなかったため、活動時間をずらして探索している可能性があります。また、迷子になり巣に戻れなくなったことも考えられます。
昼にネズミが部屋に出た場合
ネズミが昼に活動しなくてはならない理由があると予測されます。
昼にネズミが出る理由とは:ネズミが異常に増えたことや、人間の活動に適応しているから。
ネズミは本来、昼間は隠れて休んでいます。
ネズミが増えて巣が崩壊した可能性や、マンションのテナント開業、付近にある24時間営業の飲食店などにより、昼間でもエサが手に入る環境が影響しているのかもしれません。また、病気による異常行動の可能性も考えられます。
ネズミは昼間どこにいる?また、家からネズミを追い出す方法とは?ネズミが嫌いな匂いと、音などを使用する方法を解説。
夜にネズミが部屋に出た場合
通常の活動時間であり、巣が近くにあると予測されます。
夜にネズミが出る理由とは:夜行性のネズミが安心して食べ物を求めて探索できる環境になっているから。
人が寝静まると気配がなくなり、ネズミは安心して台所やゴミ箱周辺を探索し始めます。また、繁殖期を迎えた若いネズミが、新たな生息場所を求めて活発に移動していることも考えられます。
『部屋にネズミが出た』まとめ
結論として、ネズミはすでに家の中に侵入し、巣を作ってすみ着いている可能性が高いと考えられます。
また、朝や昼など通常は活動しない時間に見かけた場合は、生活環境の変化や巣の崩壊、あるいは病気のネズミが異常行動を起こしている可能性があるため、状況を見極めて適切に対処することが重要です。
しかし、焦って対処すると、害虫を呼び寄せる原因になることがあります。
そこで、虫が苦手な人の『やってはいけないネズミ対処法』として3つのポイントを紹介します。
虫が苦手な人の『やってはいけないネズミ対処法』
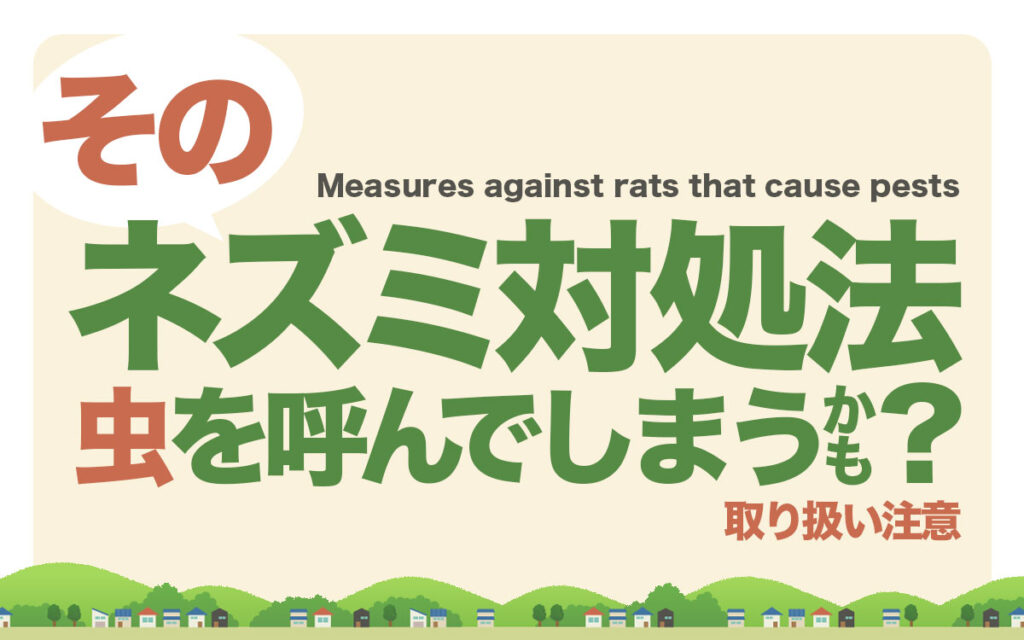
ネズミ対策として、通販やホームセンター、薬局などでさまざまな便利なアイテムが販売されています。しかし、焦って対処すると、追い払うつもりが逆に害虫を呼び寄せてしまうことがあります。
最悪なのは、ネズミの被害が解決しないばかりか、害虫まで発生してしまうことに…
便利なネズミ対策アイテムである「唐辛子・チリパウダー」「粘着シート」「殺鼠剤(さっそざい:毒餌)」ですが、対処法を間違えると、なぜ害虫が発生するのでしょうか?
次の項目では、「ネズミ対処法が害虫を呼んでしまう理由」 について詳しく解説します。
ネズミ対処法 1:唐辛子・チリパウダーでネズミ撃退 → 害虫の餌になる
結論から言うと、カプサイシン(唐辛子成分)は確かにネズミは嫌います。
しかし、香りの成分は思ったより早く消え、放置すると逆効果になることがあります。
| 放置した唐辛子などに集まる虫 | 特徴 |
|---|---|
| ゴキブリ | 何でも食べる代表的な害虫。 |
| チャタテムシ | 1〜2mmと小さく、ダニ類と誤認されやすい。 |
| ヒメマルカツオブシムシ | 幼虫は4mmほど、コショウや羽毛、革製品なども食べる。 |
| シバンムシ | 書籍やタバコ、小麦粉なども食べる |
| コナダニ | 0.3〜0.5mm。あらゆる食品類やカビも食害する。 |
湿気が多い場所ではカビも発生し、これらの害虫がさらに大量発生の原因となることがあります。特にコナダニはアレルギーの原因となるため注意が必要です。また、唐辛子がなくなった後も、そこに集まった害虫がエサを求めて被害を拡大する可能性があります。
ネズミ対処法 2:ネズミ粘着シートを放置 → ウジ・ゴキブリが発生
粘着シートでネズミを捕獲した場合、死骸をそのまま放置するのは絶対にNGです。回収しないと、腐敗が進み、ウジや害虫がたかり健康被害にもつながります。
| ネズミの死骸に集まる虫 | 特徴 |
|---|---|
| ハエ | ネズミのフンなどにも産卵、ウジが発生する。 |
| ゴキブリ | 病原菌やアレルゲンと問題が多い不快害虫。 |
| アリ | 屋外からも侵入するが、壁の中や床下にも巣を作る。 |
| ワラジムシ | ダンゴムシに似た形だが、丸くならない。 |
設置場所を忘れたり、ネズミの死骸を回収せずに放置すると、ウジが湧き、腐敗臭が漂い悪臭の原因になります。その後の処分の手間も増え、害虫の発生リスクがさらに高まります。
ネズミ対処法 3:殺鼠剤(毒餌)で駆除 → 見えない場所で死んで害虫発生
殺鼠剤は、ネズミが摂取して数日後に死亡するタイプが多いため、「どこで死ぬかわからない」 のが最大のデメリットです。
| 殺鼠剤(毒餌)によるリスク |
|---|
| 壁の中・床下・天井裏で死骸が腐敗し、ハエやウジが大量発生する。 |
| ネズミに寄生していたイエダニが宿主を失い、ヒトやペットを襲う。 |
| 腐敗臭が発生し、ゴキブリなどの害虫を屋外から引き寄せる。 |
粘着シートと違い、どこで死んでいるかわからないため、腐敗した死骸の異臭やハエの大量発生で初めて気づくケースもあります。また、宿主を失ったイエダニがヒトやペットを刺し、吸血被害を引き起こすことも少なくありません。さらに、腐敗臭がゴキブリなどを引き寄せ、害虫の発生を招く原因となるため注意が必要です。
『やってはいけないネズミ対処法』の3つのポイント
- 唐辛子・チリパウダーなどを放置しない(カビも発生し害虫を引き寄せる)。
- 粘着シートのネズミを放置しない(腐敗してウジ・ゴキブリが発生)。
- 殺鼠剤を使う場合は、死骸の発見が難しくなると感じたら使用を避ける。
便利なネズミ対策グッズも、使い方を間違えると、かえって害虫を呼び寄せる原因になります。
どこにネズミがいるのかをラットサイン(ネズミの痕跡)で確認し、「やってはいけないポイント」に注意することが大切です。
「姿は見えないけど、家の中にネズミがいる……?」不安だから確かめたい!専門家も確認する【ネズミがいるか確かめる12のチェックリスト】で紹介。
焦らず、放置せず、正しい使い方とこまめな確認・後処理を心がけることが、ネズミも虫も寄せつけない効果的な対処につながります。
よくある質問
- ネズミが出る時期はいつですか?
- ネズミは一年を通して活動していますが、特に秋から冬にかけては室内への侵入リスクが高まります。寒さを避けて暖かい場所を求めるため、家の中に侵入することが増えます。また、春と秋は繁殖期にあたり、巣作りのために活動が活発になります。巣の材料を集めるために移動が増え、侵入経路が確保されていると、室内に巣を作る可能性が高まります。
- 家にネズミがいる確率はどれくらい?
- 家にネズミがいる確率は、建物の構造や管理状態、周辺環境、季節によって大きく異なります。特に、隙間が多い家や古い建物、ネズミ対策が不十分な家では、発生する確率が高くなります。また、秋から冬にかけては、寒さを避けるために室内への侵入が増える時期です。ネズミの侵入リスクを低減するには、家の隙間を塞ぐ、食品を適切に管理する、こまめな清掃を行うなどの対策が重要です。屋内で足音やフン、かじられた跡を見つけた場合は、早めに対処する必要があります。
- 部屋にネズミが出たら?
- 部屋にネズミが出るのは、すでに家の中に侵入されている可能性が高いといえます。ネズミは通常、人目につかない場所で活動しますが、巣が崩壊して移動してきた場合や、やむを得ずエサを求めて探索しているなど、通常とは異なる理由で部屋に姿を現すことがあります。これは、家の中でネズミの環境に何らかの異常が起きているサインかもしれません。慎重に状況を確認することが大切です。
まとめ
- ネズミが部屋に出たら家の中に巣がある可能性を考えて対処する。
- 朝や昼にネズミを見かけた場合は病気の異常行動も考えられるので個人では無理に対処しない。
- 夜に見かけた場合はネズミが繁殖のために巣を広げている可能性がある。
- 間違ったネズミ対策アイテムの使い方、対処法は虫が発生するので注意する。
ネズミの対処法には思わぬ二次被害を招く恐れがあります。忌避剤の唐辛子やハーブ類、粘着シート、殺鼠剤などを使用する前に侵入経路を塞ぎ、定期的に確認することが重要です。また、対処後には消毒と清掃を徹底し、害虫の発生を防ぎましょう。

監修:引田 徹【クリーン計画プロープル株式会社:施工部長】
取材担当:フジテレビ「ライブニュースイット」|BS-TBS「噂の!東京マガジン」|テレビ朝日「スーパーJチャンネル」|日本テレビ「news every.」|テレビ朝日「報道ステーション」|フジテレビ「めざまし8」|テレビ朝日「グッド!モーニング」|テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」|日本テレビ「DayDay.」|TBSテレビ「THE TIME,」|そのほか多数メディア出演対応(順不同)
資格:(公社)日本ペストコントロール協会|(公社)神奈川県ぺストコントロール協会|(一社)日本有害生物対策協会|日本ペストロジー学会|(公財)文化財虫菌害研究所|しろあり防除施工士|建築物ねずみ昆虫等防除業登録|(一社)日本鳥獣被害対策協会|セントリコン・テクニカル・マスターなどその他にも多数の資格を保有
<参考文献>:緒方 一喜、住環境の害虫獣対策、日本環境衛生センター、2015、p.497、
<参考文献>:日本家屋害虫学会、家屋害虫事典、井上書院、1995、p.468、