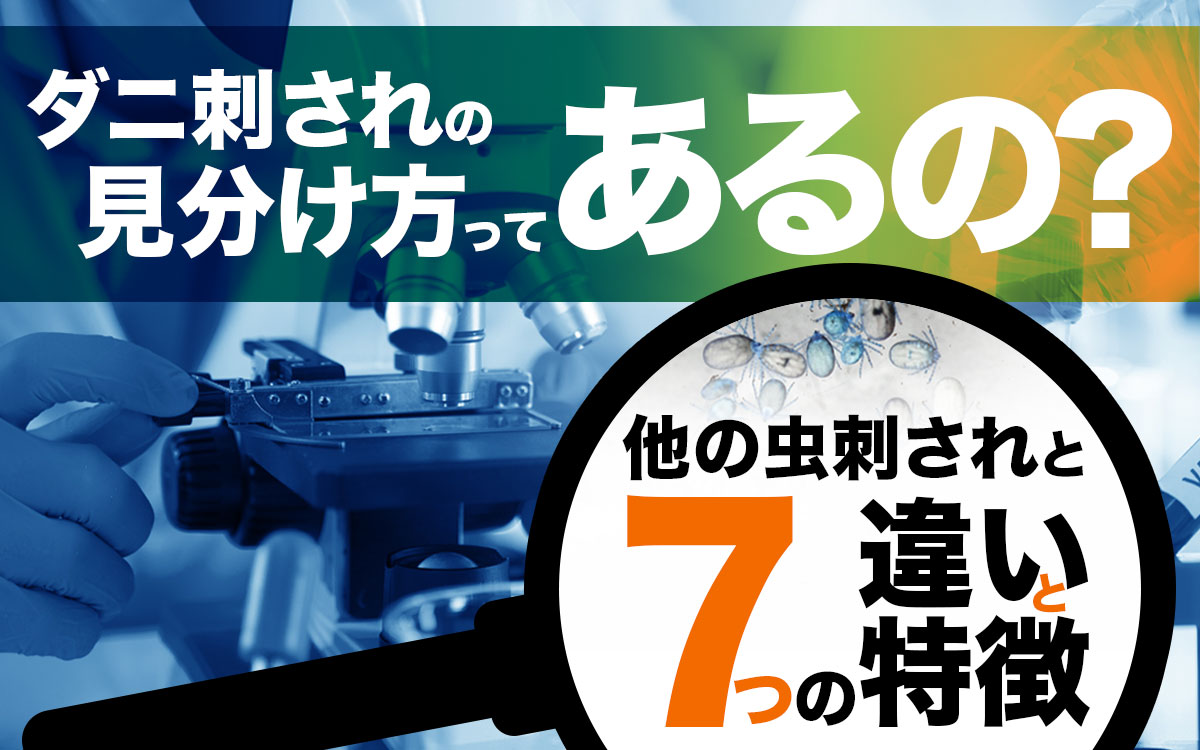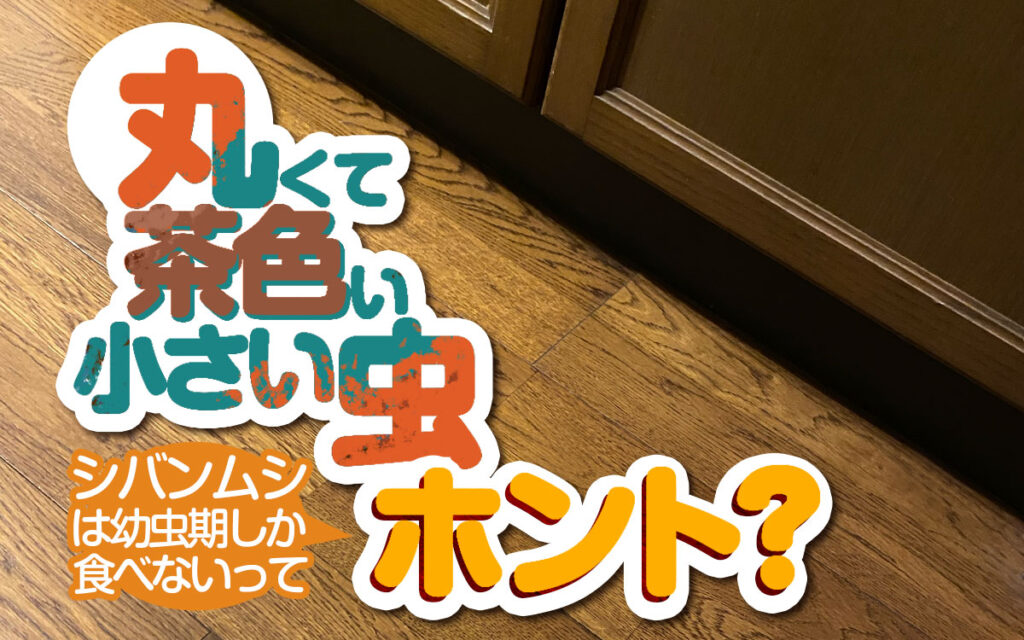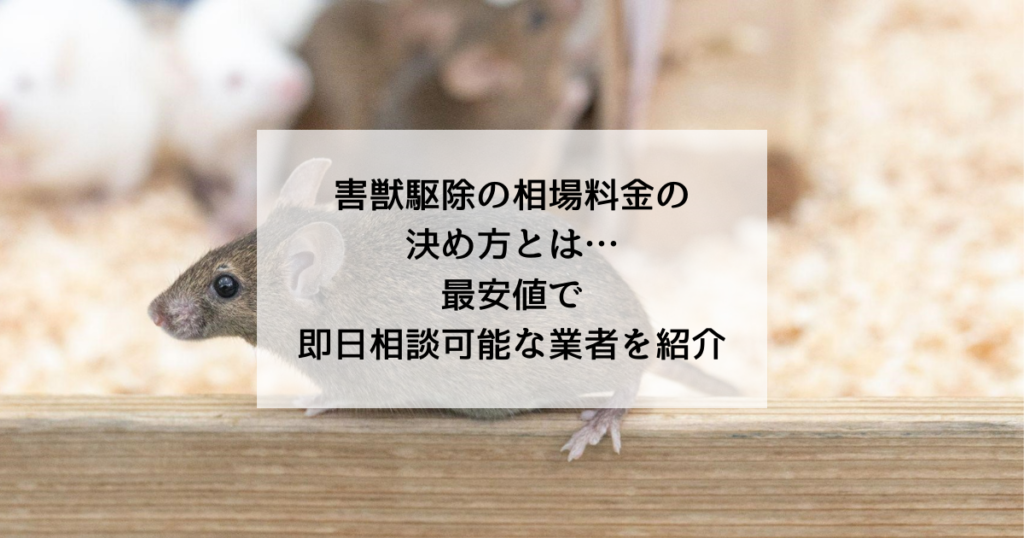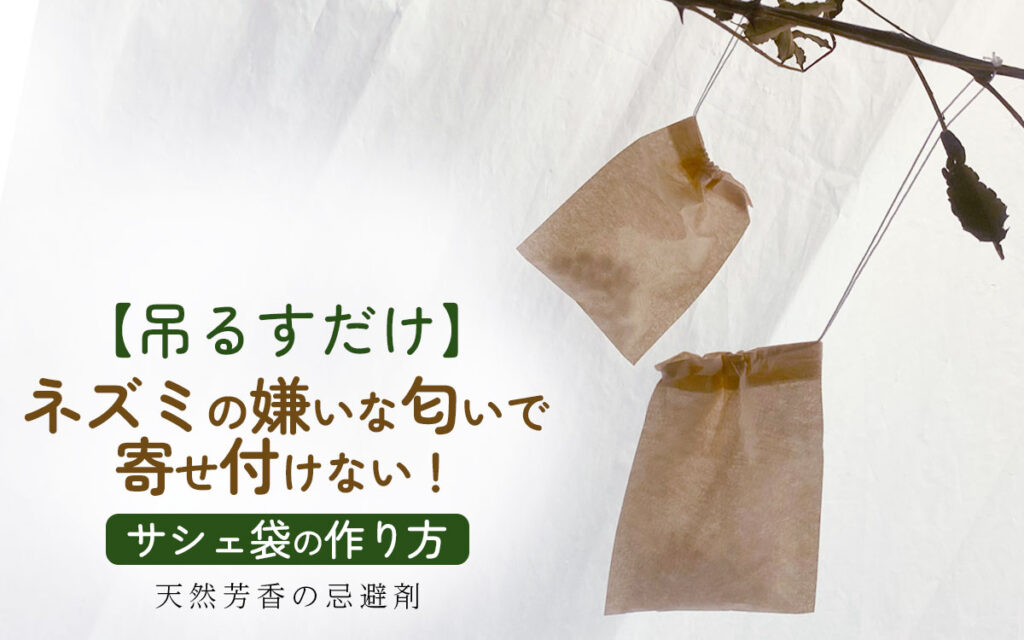こんにちは、プロープル広報のkikuです。
テレビやニュースで「マダニに噛まれて重症化」という話を聞いて、心配になったことはありませんか?
マダニは野山、とくに藪や草むらに多く生息していますが、散歩中に犬に付着し、そのまま庭や家の周りに住み着いて被害が出ることもあります。
小さな体でも危険な病原体を持っているため、注意が必要です。
では、もしマダニに噛まれたら、どんな症状が出るのでしょうか。
今日のテーマは、【マダニに噛まれたら】どんな症状が出るの?をくわしく解説しました。
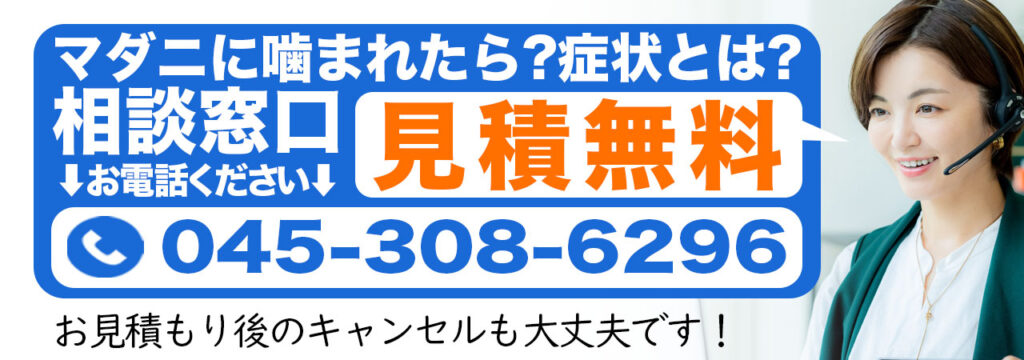
マダニに噛まれたら最初にすべきこと

マダニに噛まれたらどう対処したら良いのでしょうか?
結論:無理に引き抜かず、速やかに医療機関(皮膚科)へ。
マダニの口器には、皮膚を切り開く鋭い刃のような鋏角(きょうかく)と、皮膚に深く食い込み抜けにくくするノコギリの歯のような口下片(こうかへん)があり、これらを使って深く噛みつき固定します。
無理に取ると、マダニの口器の一部が皮膚に残って膿んだり、唾液や体液が逆流して病原体による感染症リスクが高まります。
なぜ自分で取ってはいけないのか?

マダニは特殊な口器の仕組みから、自分で取ってはいけない理由があります。
理由:口器が皮膚に残りやすいためです。
なぜ残りやすいのかというと、鋭く特殊な口器に加え、吸血中に分泌される“乳白色のセメント様物質(接着剤のような物質)”によって、皮膚に強く固定されます。
そのため、力ずくで取ろうとすると体から口器だけがちぎれて皮膚内に残ってしまいます。
口器が残ると危険な理由?
残った口器は化膿や肉芽腫(にくげしゅ:炎症によるしこり)の原因となり、さらに唾液や体液が逆流して感染症のリスクが高まります。局所の炎症にとどまらず、マダニが媒介する病原体が体内に入り込む危険性もあるため、必ず医療機関での処置が必要です。
マダニと病原体の関係
- 無理に引き抜くと、唾液や消化液が逆流する。
- 唾液や消化液には病原体が含まれる場合がある。
- 体内に入ると感染症のリスクが高まる。
マダニを含め、ダニの種類によって刺された後の症状は大きく異なります。見分け方を知っておくことは、ダニ対策にも役立ちます。
ダニ刺されの見分け方とは?他の虫刺されと7っの違いと特徴を解説しました。
ダニの中でも特に危険なマダニに噛まれた場合には、どのような症状が現れるのか。ここからは、その特徴を詳しく見ていきましょう。
マダニに噛まれたらどんな症状が出るの?
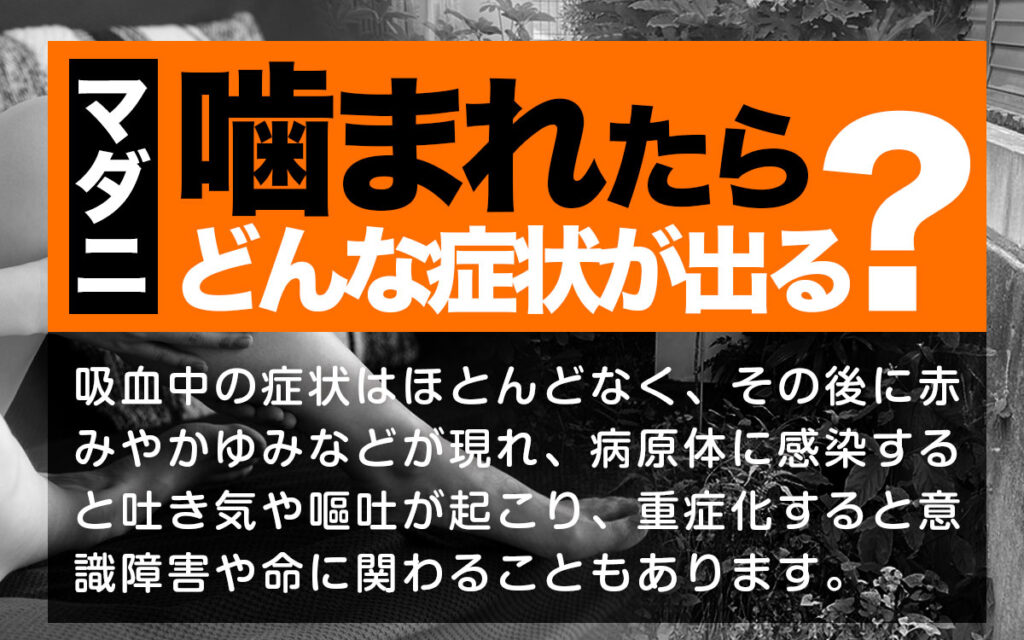
吸血中はかゆみや痛みがほとんどなく、発見が遅れやすいのが特徴です。
症状は、噛まれた箇所の変化と体全身の症状に大きく分けられます。
噛まれた箇所や周辺の変化
- 吸血後、皮膚の赤みや腫れが出て、その後かゆみが出ることがある。
- 病原体が侵入した場合、紅斑(こうはん:皮膚が赤くなる)や潰瘍(かいよう:皮膚や粘膜がくずれた傷)になることもある。
- マダニに長期間、噛まれていた場合や、口器の一部が残った場合、膿や肉芽腫(にくげしゅ:炎症反応によってできるしこり)が形成されることがある。
体の全身症状
- 発熱や体のだるさ、頭痛、筋肉の痛み。
- 吐き気や嘔吐、下痢、食欲の低下などの消化器症状。
- 重症化すると意識障害や出血傾向が見られることがあります。
【マダニに噛まれたら、どんな症状が出る?】のまとめ
- マダニに噛まれたら:無理に引き抜かず、すぐに皮膚科など医療機関へ。
- 吸血中の特徴:かゆみや痛みがほとんどなく、発見が遅れやすい。
- マダニの口器とは:鋭い刃のような鋏角(きょうかく)で皮膚を切り、ノコギリ状の口下片(こうかへん)で深く固定。
- 自分で取る危険性:口器の一部が皮膚に残って化膿や肉芽腫の原因になる/唾液や体液が逆流して感染症の危険が高まる。
- 噛まれた箇所の症状:赤み、腫れ、かゆみ/紅斑や潰瘍になることも/長期間付着や口器残存で膿や肉芽腫ができることがある。
- 全身症状:発熱、だるさ、頭痛、筋肉痛/吐き気、嘔吐、下痢、食欲低下/重症化で意識障害や出血傾向。
病院に行かないとどうなるの?

結論:マダニは複数の感染症を媒介しますので危険です。
受診せず放置すると、症状が進行して重症化し、命に関わる場合もあります。
マダニが媒介する感染症と進行リスク
- 日本紅斑熱、SFTS(重症熱性血小板減少症候群)、ライム病など複数の感染症を媒介する。
- 治療が遅れると、発症・重症化の危険が高まる。
- 一部の感染症は致死率が高く、回復後も長期の後遺症が残る場合ある。
主な感染症と進行後の症状一覧
以下は、主な感染症と進行後の症状を一覧でまとめました。
| 感染症名 | 主な症状 | 進行後の症状 |
|---|---|---|
| 日本紅斑熱(にほんこうはんねつ) | 高熱、全身の発疹、頭痛 | 多臓器障害、死亡例あり |
| SFTS(重症熱性血小板減少症候群) | 発熱、消化器症状(嘔吐・下痢)、血小板減少 | 致死率が高い、意識障害、出血傾向 |
| ライム病 | 発熱、倦怠感、遊走性紅斑(ゆうそうせいこうはん) | 関節炎、神経症状、心障害 |
| 回帰熱(かいきねつ) | 発熱、悪寒、筋肉痛 | 繰り返す発熱発作 |
| 野兎病(やとびょう) | 発熱、リンパ節腫脹、潰瘍(かいよう) | 重症化で敗血症(はいけつしょう) |
マダニを除去した後に注意することは?

医療機関でマダニを除去した後も、油断は禁物です。
その理由とは、感染症は潜伏期間があるため、診断後もしばらくは体調の変化に注意しましょう。
経過観察期間と注意点
- 除去日から少なくとも2週間は、毎日体温と体調を確認する。
- 発熱、発疹、倦怠感、頭痛、筋肉痛、吐き気、下痢などが出たらすぐ再受診。
- 感染症である日本紅斑熱やSFTSなどは早期治療が重要なため、症状を軽く見ない。
刺された部位のチェック
- 赤みが広がる、腫れが強くなる、膿が出る、しこり(肉芽腫:にくげしゅ)ができる場合は要注意。
- 潰瘍(かいよう)や化膿がある場合は細菌感染の可能性があるため早めに受診。
記録を残す
- 除去日、噛まれた場所(山、草地、公園、庭など)、活動内容(散歩、農作業、キャンプなど)を記録しておきましょう。
- 容態が急変し救急搬送されるような緊急時には、この記録が診断や治療の重要な糸口になります。
マダニに噛まれないための予防策
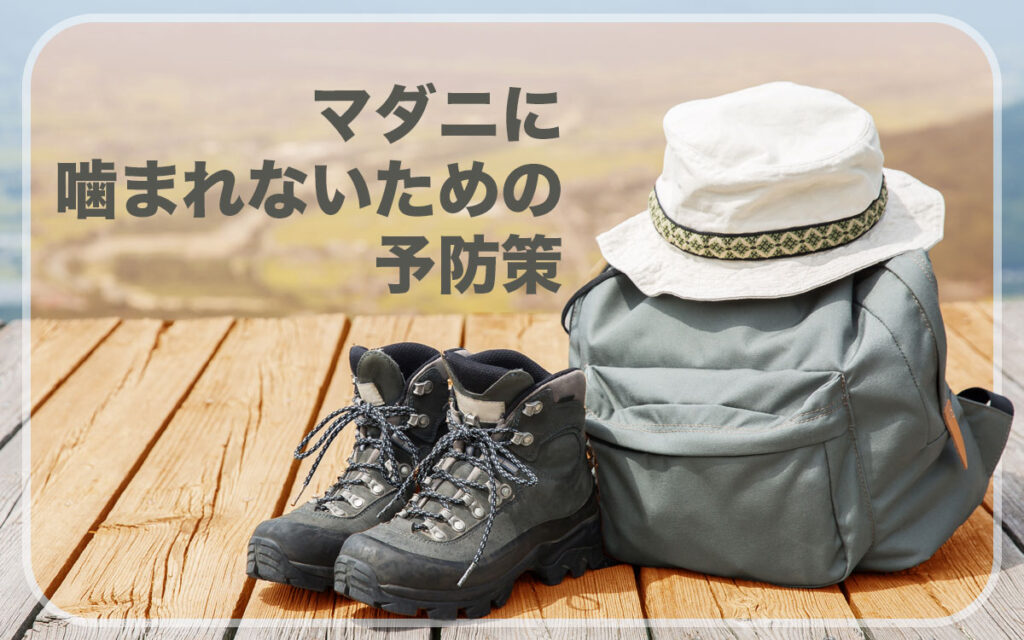
屋外での活動時は、マダニに噛まれないよう次のような対策を心がけましょう。
服装でマダニから防御
- 野山や藪・草むらに入るときは、長袖・長ズボンを着用する。
- シャツの袖口は手袋の中に入れ、ズボンの裾は靴下で覆う。
- 帽子や手袋を着用し、首にタオルを巻き肌の露出を防ぐ。
虫よけ剤の使用
- 濃度10%前後の「ディート」を忌避剤として手袋や袖口にスプレーすると、2〜3時間効果が期待できる。
- 「イカリジン」を含む忌避剤を衣服に使用する。
屋外活動後の確認
- 衣服や靴、体にマダニがついていないか確認し、入浴で全身を洗い流す。
注意点
虫よけ剤の使用には注意が必要です。年齢制限や、化学繊維・皮革などを傷めるおそれがあります。忌避剤の使用でマダニの付着数は減少しますが、完全に防げるわけではありません。さまざまな防護手段と組み合わせて対策をすることが大切です。
ペットと野生動物とマダニの関係

マダニは、里山や草むらなどの野外に生息しています。登山や野山の散策ではもちろん対策が必要ですが、実は出歩かなくても噛まれる危険がある場所があります。
それは庭です。
シカ、イノシシ、タヌキなどの野生動物もマダニの寄生元となり、庭や畑に侵入するとマダニを生活圏に持ち込むことがあります。
持ち込まれたマダニは、人やペットなどを吸血する機会をうかがっています。
犬や猫は屋外でマダニが付着しやすく、散歩から帰ったときにそのまま家の中へ持ち込んでしまうことがあります。
また、庭の雑草や伸び放題の庭木は、マダニをはじめ害虫の住処になりやすいため、こまめに草刈りや庭木の手入れをして、マダニが住みにくい環境を保ちましょう。
そのため、庭木のお手入れに加えて、ペットのケアや野生動物の侵入を防ぐ工夫も大切です。
よくある質問
- マダニに刺されたらどうなるの?
- 結論:病原体を媒介し、感染症などの重い病気を引き起こすおそれがあります。早めに皮膚科で除去しましょう。
マダニは幼虫・若虫・成虫のいずれの時期でも哺乳類や鳥類、爬虫類に寄生して吸血します。吸血期間は数日から1週間以上と長く、「食いついたら離れない」ため、無理に引き抜くと口器が皮膚に残り化膿することがあります。医療機関で適切に除去してもらうことが大切です。 - マダニに噛まれてから何日で症状が出る?
- 結論:感染症によって異なりますが、多くは数日から2週間程度で発症します。
マダニが媒介するSFTS(重症熱性血小板減少症候群)は、噛まれてから6日〜2週間ほどで発熱や消化器症状が現れることがあります。日本紅斑熱では2〜8日程度、ライム病では3日〜1か月と幅があります。いずれも潜伏期間中は自覚症状がないため、噛まれたことに気付かず症状が出る場合があります。噛まれた場合は無症状でも速やかに医療機関で診察を受けることが重要です。 - マダニは家の中でどこにいるの?
- 結論:ペット周辺など、寄生元の動物が出入り・滞在する場所に潜んでいます。
マダニは本来、野外の草むらや藪などに生息しますが、犬や猫などのペット、またはシカやイノシシなどの野生動物が庭や家屋周辺に侵入すると、その体に付着したまま室内に持ち込まれることがあります。家に持ち込まれたマダニは、ペットの寝床やケージ周辺、玄関付近など、人や動物が頻繁に出入りする場所に潜みます。
まとめ
- マダニに噛まれたら:無理に引き抜かず、すぐに皮膚科など医療機関へ。
- 吸血中の特徴:かゆみや痛みがほとんどなく、発見が遅れやすい。
- マダニの口器とは:鋭い刃のような鋏角(きょうかく)で皮膚を切り、ノコギリ状の口下片(こうかへん)で深く固定。
- 自分で取る危険性:口器の一部が皮膚に残って化膿や肉芽腫の原因になる/唾液や体液が逆流して感染症の危険が高まる。
- 噛まれた箇所の症状:赤み、腫れ、かゆみ/紅斑や潰瘍になることも/長期間付着や口器残存で膿や肉芽腫ができることがある。
- 全身症状:発熱、だるさ、頭痛、筋肉痛/吐き気、嘔吐、下痢、食欲低下/重症化で意識障害や出血傾向。
野外に生息しているマダニは、思わぬ場所で被害が確認されることもあります。
マダニをはじめとする害虫を発生させないためにも、庭木の管理は防除として有効です。当社では、庭木や雑草の管理、庭を横断する害獣対策、マダニの防除もお任せください。

監修:引田 徹【クリーン計画プロープル株式会社:施工部長】
取材担当:フジテレビ「ライブニュースイット」|BS-TBS「噂の!東京マガジン」|テレビ朝日「スーパーJチャンネル」|日本テレビ「news every.」|テレビ朝日「報道ステーション」|フジテレビ「めざまし8」|テレビ朝日「グッド!モーニング」|テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」|日本テレビ「DayDay.」|TBSテレビ「THE TIME,」|そのほか多数メディア出演対応(順不同)
資格:(公社)日本ペストコントロール協会|(公社)神奈川県ぺストコントロール協会|(一社)日本有害生物対策協会|日本ペストロジー学会|(公財)文化財虫菌害研究所|しろあり防除施工士|建築物ねずみ昆虫等防除業登録|(一社)日本鳥獣被害対策協会|セントリコン・テクニカル・マスターなどその他にも多数の資格を保有
<参考文献>:近藤 繁生 ほか、わが家の虫図鑑 (新装改訂版)、トンボ出版、2015、p.151、
<参考文献>:C.オトゥール ほか、動物大百科 15 昆虫、平凡社、1987、p.171、
<参考文献>:緒方 一喜 ほか、住環境の害虫獣対策 改訂版、日本環境衛生センター、2015、p.497、