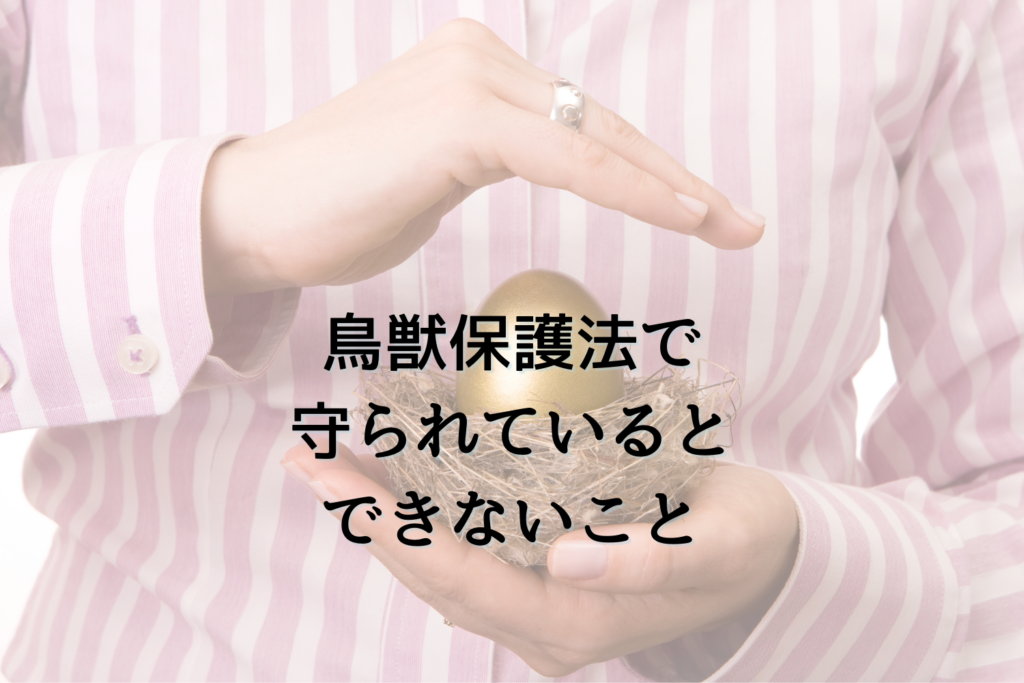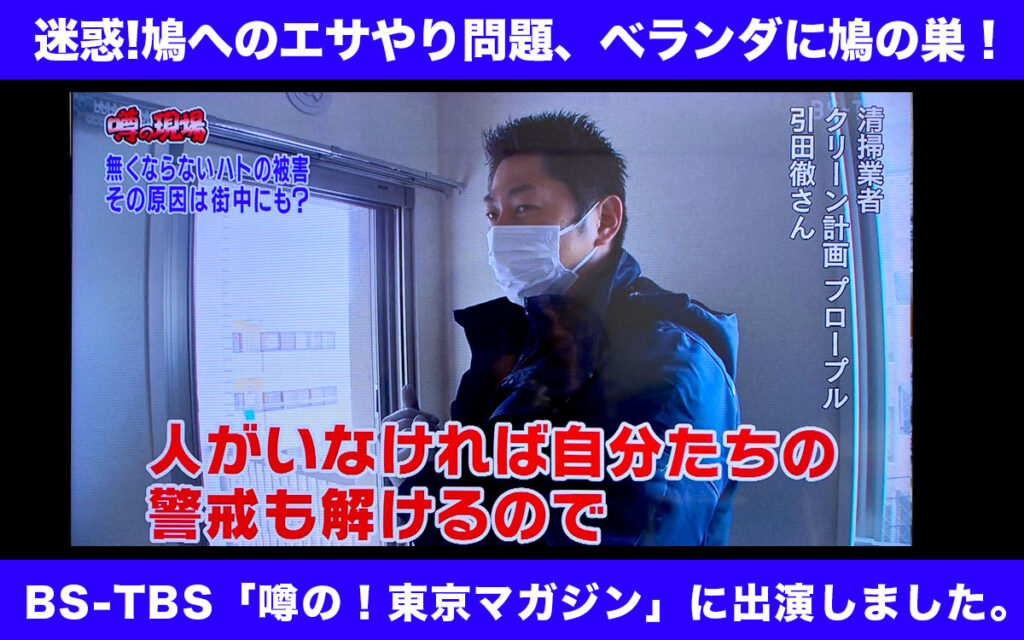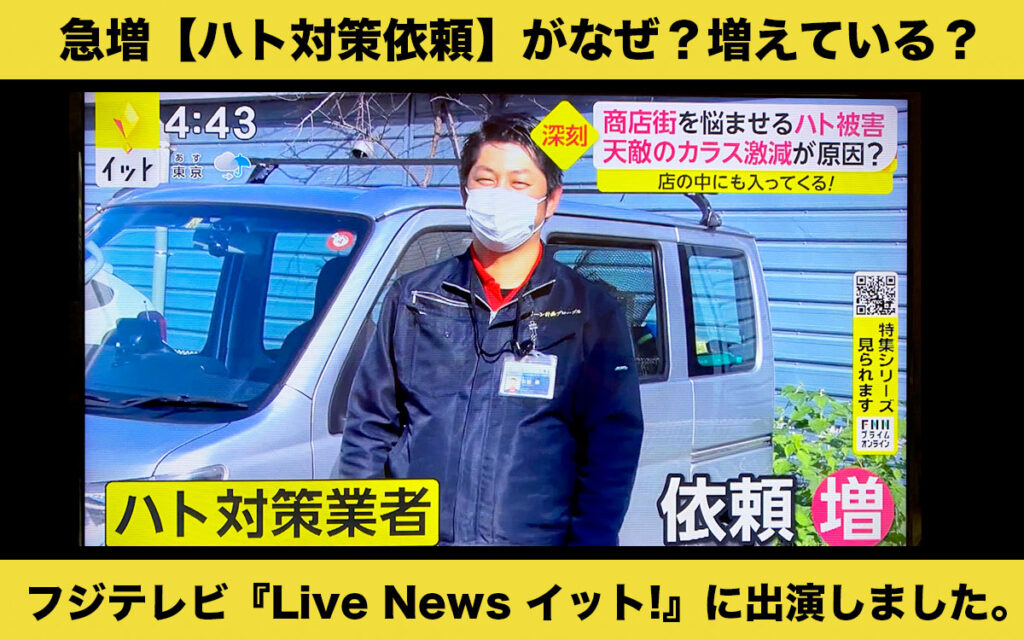こんにちは、プロープル広報のkikuです。
「コウモリって、やっぱり汚いの?」
わずかな隙間から家に入り込み、屋根裏や換気口に住み着きフンを落としていたら……「病気がうつる?」「コウモリの菌って何?」「空気感染するの?」と不安になるのも当然です。
特に小さな子どもや妊婦さん、高齢者がいるご家庭では、家族への影響が気になりますよね。
今日のテーマは、「コウモリは本当に汚いのか?」そして、空気感染やコウモリの菌・病気、家族への影響とその対策までをわかりやすく解説していきます。
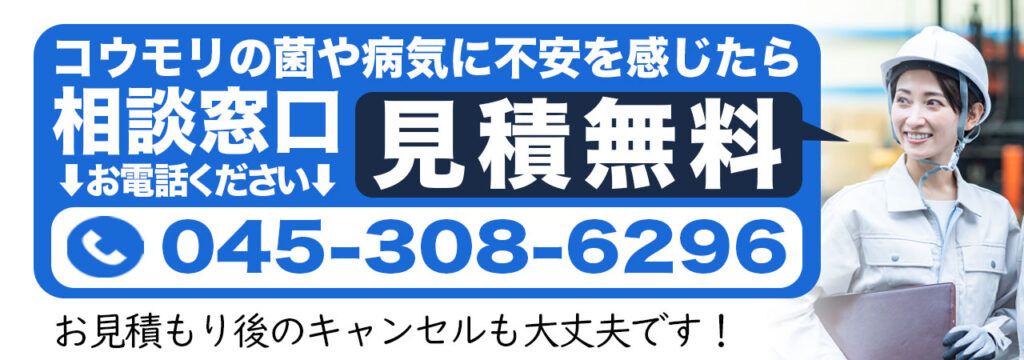
コウモリって本当に汚いの?なにが汚いの?
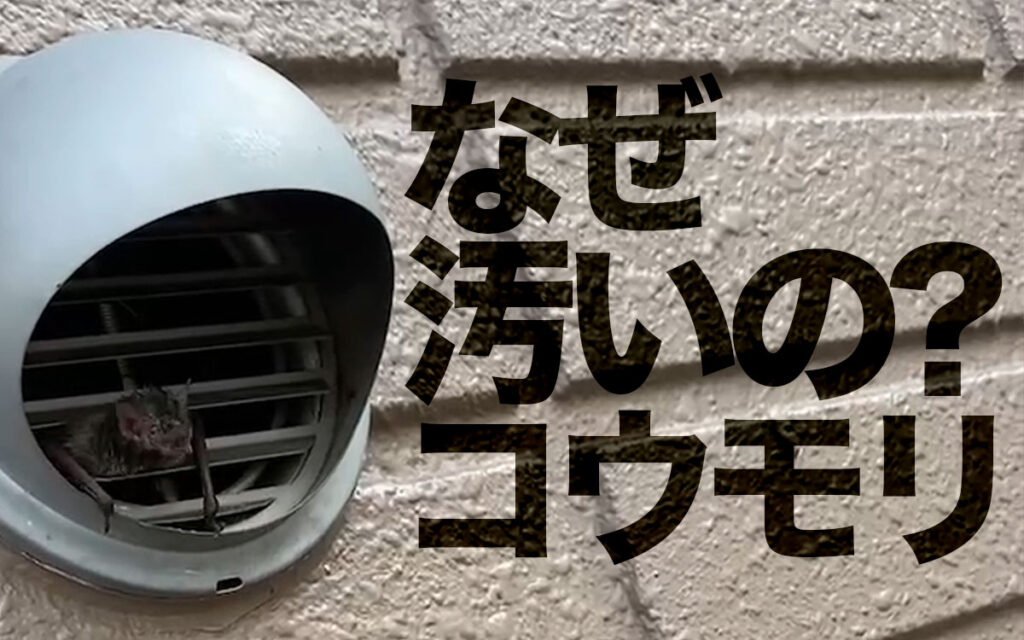
コウモリって何が「汚い」とされる原因なのでしょうか?
原因:家に住み着いたコウモリは、大量のフン尿によるカビの繁殖や、体に寄生するダニやトコジラミの拡散によって、住み着いた場所に深刻な衛生被害をもたらすため、「汚い」といえます。
ちなみに、日本の住宅や建築物に住み着くコウモリの中で、最も一般的なのはアブラコウモリ(別名:イエコウモリ)です。屋根裏や換気口、戸袋、外壁のわずか1cmほどのすき間からでも侵入することができます。
一度住み着くと同じ場所を長期間使い続け、アレルギーや皮膚症状などの健康被害につながるおそれがあります。
外壁や駐車場などにフンが落ちている

昆虫を餌とするアブラコウモリは夜間、街灯周辺や住宅の外壁、陸橋の構造物などにとまり、休憩することがあります。
その際に排泄されたフンが、建物の外壁やベランダ、さらには屋外の駐車場に点々と落ちているケースが各地で報告されています。
乾燥したフンは崩れやすく、車や洗濯物を汚す原因となることも少なくありません。
室内では屋根裏や換気口がフン尿まみれに
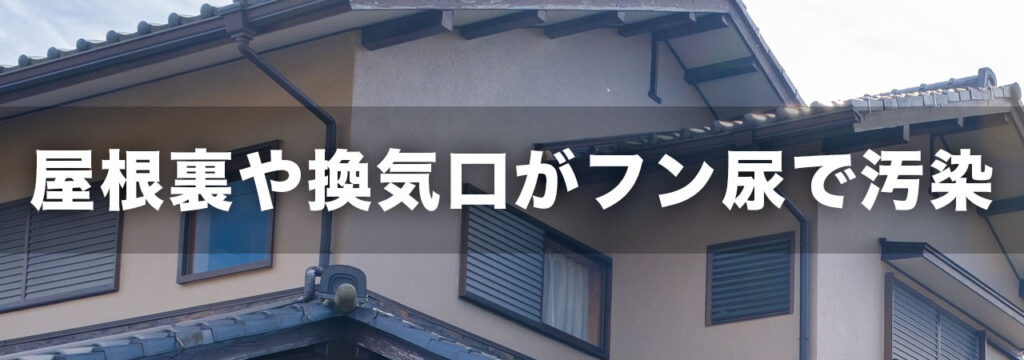
建物に侵入したアブラコウモリは、屋根裏や戸袋、換気口の内部など、狭くて暗い空間を好んでねぐらにします。
一度住み着くと、同じ場所に長くとどまり、数十~100頭以上の個体が集団で生活することもあります。
その結果、屋根裏や壁の中にフンや尿がたまり続け、悪臭や天井の腐食、カビの発生など、いつの間にか深刻な被害が広がっていることもあります。
こうした被害を防ぐには、コウモリがなぜ家に入り込み、どこを対策すべきかを知ることが重要です。詳しくはこちらをご覧ください → 「コウモリの対策は軒下にあった!」
住み着いた場所では菌・カビ・ダニ・トコジラミも繁殖する

アブラコウモリが住み着いた場所では、フン尿の蓄積によってカビや細菌が発生し、乾燥すると空気中に舞って室内に広がるおそれがあります。
また、ダニの仲間である「サシダニ」や「ケモチダニ類」が寄生しており、ねぐらにはダニの死骸やフンが残されます。吸血によってかゆみを伴う湿疹が生じるほか、アレルギー反応やハウスダストの原因となることもあります。
さらに、「コウモリトコジラミ」が人家に侵入し、ヒトを刺して吸血した可能性がある症例も報告されています。
このような環境は、カビ・菌・ダニ・トコジラミの温床となり、間接的ではありますが、健康被害のリスクを高める原因になります。
「コウモリは汚い?」のまとめ
コウモリが「汚い」とされるのは、その生態に原因があります。
小さなすき間から家に入り込み、屋根裏や換気口などに数十〜100頭以上が集団で住み着き、毎日フン尿を垂れ流す。その結果、木材や断熱材が腐り、カビや細菌が繁殖し、ダニやトコジラミまで発生することがあります。
外ではフンが車や洗濯物を汚し、家の中では見えないところでアレルゲンや吸血害虫が広がる可能性もあり、衛生面で深刻な被害をもたらすのです。見た目では気づかなくても、じつは家の中に静かに汚染が広がっている……そう考えると、コウモリが「汚い」とされるのも当然かもしれません。
コウモリの病気が空気感染する?
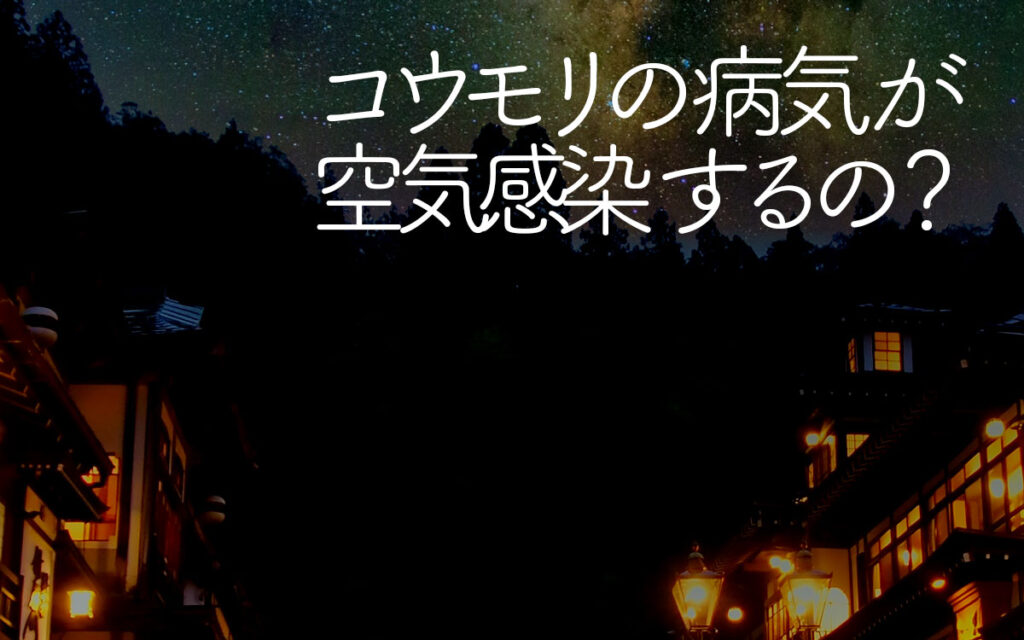
コウモリが家に住み着いていたり、近くを飛んでいるだけで「病気が空気感染するのでは」と不安になる方もいるかもしれません。
では、実際に空気感染することはあるのでしょうか?その他の感染リスクとは何があるのでしょうか?
結論:家に住み着く「アブラコウモリ」から病気が空気でうつることは基本的にありませんが、フンに含まれるカビの胞子が空気中に舞い、それを吸い込むことで肺に炎症が起こる「吸入性感染(きゅうにゅうせいかんせん)」の可能性があります。
中でも「ヒストプラズマ」は、海外での発症が多く、乾燥したフンが粉じん化して空気中に舞い、それを吸い込んで感染するケースが知られています。日本ではごくまれですが、屋根裏や換気口の清掃時などには注意が必要です。
では、その他の感染リスクとは何があるのでしょうか?
アブラコウモリと人との接触パターンを踏まえて、具体的に見ていきましょう。
コウモリに噛まれたときは?

狂犬病ウイルスを持つコウモリが海外では確認されていますが、日本のコウモリからは今のところ発見されていません。
ただし、未知のウイルスが存在する可能性も否定できないため、万が一コウモリに噛まれた場合は、念のため医療機関を受診することをおすすめします。
また、噛まれていなくても、フンや尿に含まれるカビや細菌、寄生虫などの危険性もありますので素手では絶対に触らないでください。
コウモリに近づいただけで感染する?

コウモリにただ近づいただけで感染することは、基本的にはありません。
しかし、屋根裏や換気口、壁のすき間などのねぐらとなっている場所では、フンの粉やカビの胞子が空気中に舞っている可能性があり、これを吸い込むことで健康リスクが生じるおそれがあります。
特に、アレルギー体質の方や、呼吸器系に不安がある人、免疫力の弱い人、小さな子どもなどは、気管支ぜんそくや肺炎の引き金となる可能性も指摘されています。
コウモリに触ったら病気ってうつるの?

コウモリを素手で触っただけで、すぐに病気がうつることは基本的にありません。
ただし、体に寄生している吸血性のダニやトコジラミ、体やフンに付着したカビ・細菌などに触れることで、皮膚炎やアレルギー、感染症の原因になるおそれがあります。
傷口がある場合や、触った手で目や口・鼻などの粘膜をこすってしまった場合は、より注意が必要です。
不安なときは、すぐに石けんで手を洗い、必要に応じて医療機関に相談してください。
コウモリ菌?感染症には何がある?

「コウモリ菌」という言葉は正式な医学用語ではありませんが、実際にコウモリのフンや尿に触れたり、噛まれたり、空気中に舞い上がったカビや細菌を吸い込むことで、呼吸器や皮膚などに健康被害をもたらす病気があります。
結論:日本国内では発症例は少ないものの、フンの吸入や噛まれたなどをきっかけに感染する病気が存在するため、予防の意識は必要です。
吸い込みによる肺感染(ヒストプラズマ症)

「ヒストプラズマ(Histoplasma capsulatum)」というカビが、乾燥したコウモリのフンに含まれるカビの胞子が空気中に舞い、それを吸い込むことで肺に感染することがあります。
感染すると、咳・発熱・肺炎などの症状が出ることがあり、重症化すると「慢性肺炎(まんせいはいえん)」や全身に広がる「播種性感染(はしゅせいかんせん)」に進行することもあるとされています。
日本ではまれな「輸入感染症」ですが、コウモリが住み着いた屋根裏や換気口などの清掃時には注意が必要です。
吸い込みによる肺感染の補足解説(用語)
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 慢性肺炎(まんせいはいえん) | 数週間以上続く肺の炎症。悪化すると肺機能に影響を与える。 |
| 播種性感染(はしゅせいかんせん) | 菌やウイルスなどが血液を通じて体内全体に広がる重篤な感染症。 |
| 輸入感染症(ゆにゅうかんせんしょう) | 海外で感染し、日本国内で発症した感染症。 |
咬まれることによる致命的感染(狂犬病)
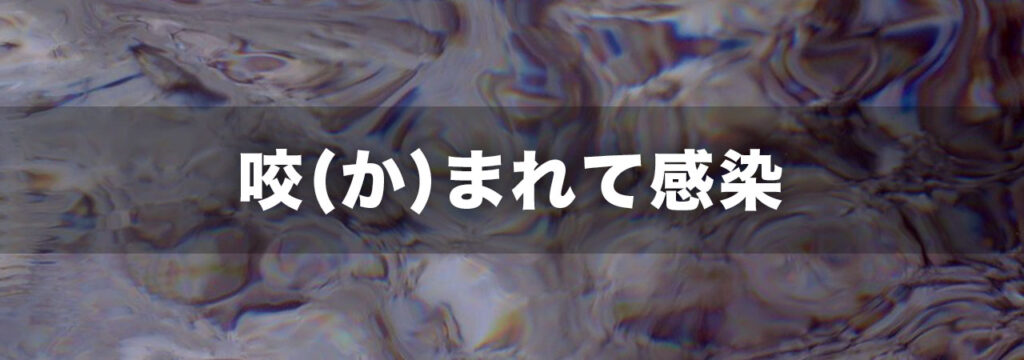
コウモリに「咬傷:こうしょう(かみ傷)」で、海外では狂犬病ウイルスに感染した事例が報告されています。
日本の野生コウモリからは今のところ狂犬病ウイルスは発見されていませんが、万が一に備えて咬まれた(噛まれた)場合は必ず医療機関を受診してください。
一度発症すると致死率が極めて高いため、海外でコウモリに噛まれた際には特に注意が必要です。
その他の感染症(クリプトコックス症・レプトスピラ症など)

コウモリのフンや尿に関係する感染症として、他にも以下のような病気が報告されています。
- クリプトコックス症:
カビの一種であるクリプトコックス属によって引き起こされ、肺や中枢神経に感染することがあります。 - レプトスピラ症:
尿を介して感染する細菌性の疾患で、発熱や筋肉痛、重症化すると黄疸や腎障害が現れることもあります。
これらの感染症は、直接の接触だけでなく、屋根裏やベランダなどに残されたフンや尿を通じても間接的に感染することがあるためコウモリが住み着いたら放置しておくのは大変危険です。
その他の感染症の補足:病原体、病原菌、ウイルス、病気の違いとは
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 病原体(びょうげんたい) | 病気を引き起こす元になるすべて(細菌・ウイルス・カビ・寄生虫など) |
| 病原菌(びょうげんきん) | 病原体の中でも「細菌(バクテリア)」を指すことが多い |
| ウイルス | 自力で増殖できず、他の細胞に寄生して増える微小な病原体 |
| 感染症(かんせんしょう) | 病原体が体に入り、増殖することで発症する病気のこと |
| 病気 | 感染症を含む、体に異常が起きているすべての状態の総称 |
コウモリの菌は子ども・妊婦さん・高齢者は特に注意?
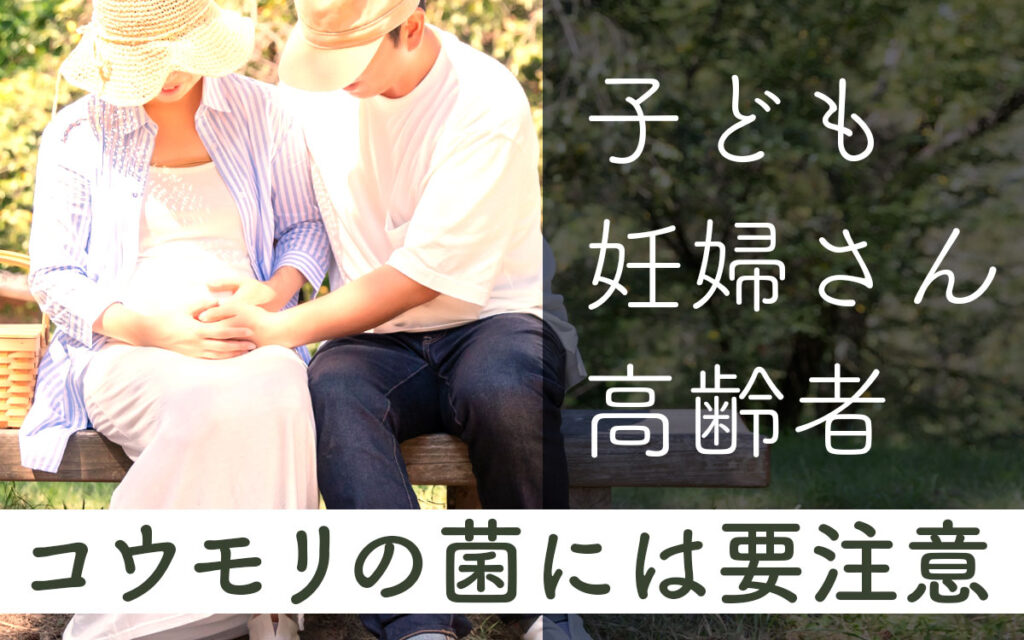
コウモリからの健康被害は、すべての人に病影響を与える可能性がありますが、とくに注意すべき人はどの様な人でしょうか?
結論:とくに子ども、妊婦さん、高齢者は、感染症やアレルギーの症状が強く出るおそれがあるため注意が必要です。
子どもや乳児は、アレルゲンやカビの影響を受けやすい

コウモリのフンは、昆虫を主食としているため繊維分が少なく、乾燥して崩れやすい性質があり、空気中に舞って吸い込まれる可能性があります。
とくに乳幼児は呼吸器が未発達で、ハウスダストやカビに敏感なため、ぜんそくや咳などの症状が出やすくなるおそれがあります。
妊婦さんは感染による影響を受けやすい
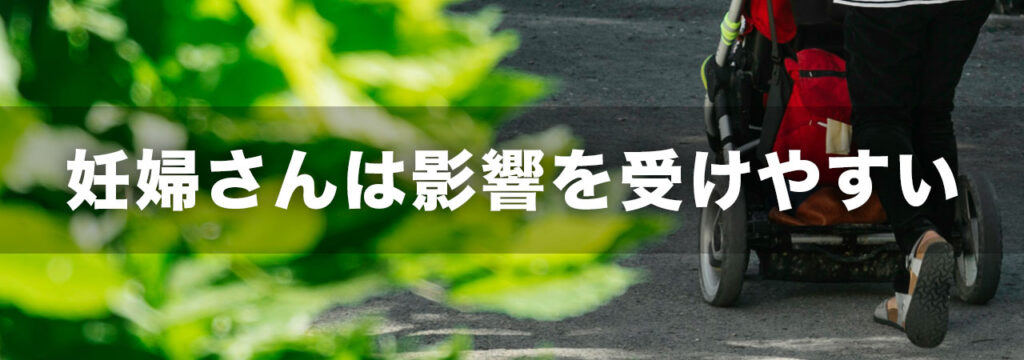
妊娠中は免疫のバランスが変化するため、感染症にかかると重症化しやすいことが知られています。
コウモリに直接触れることは少ないとしても、フンや寄生虫、カビなどが室内に広がると、コウモリが原因で思わぬ影響を受ける可能性があります。
高齢者もカビや感染症に注意が必要

高齢になると免疫機能が低下しやすく、コウモリのフンに含まれるカビの胞子を吸い込むことで、ヒストプラズマ症のような肺感染が重症化しやすくなるおそれがあります。
また、屋内で過ごす時間が長い傾向があるため、家にコウモリが住み着いた場合、その影響を受けやすく注意が必要といえます。
もしもコウモリを見つけたらどうすればいい?
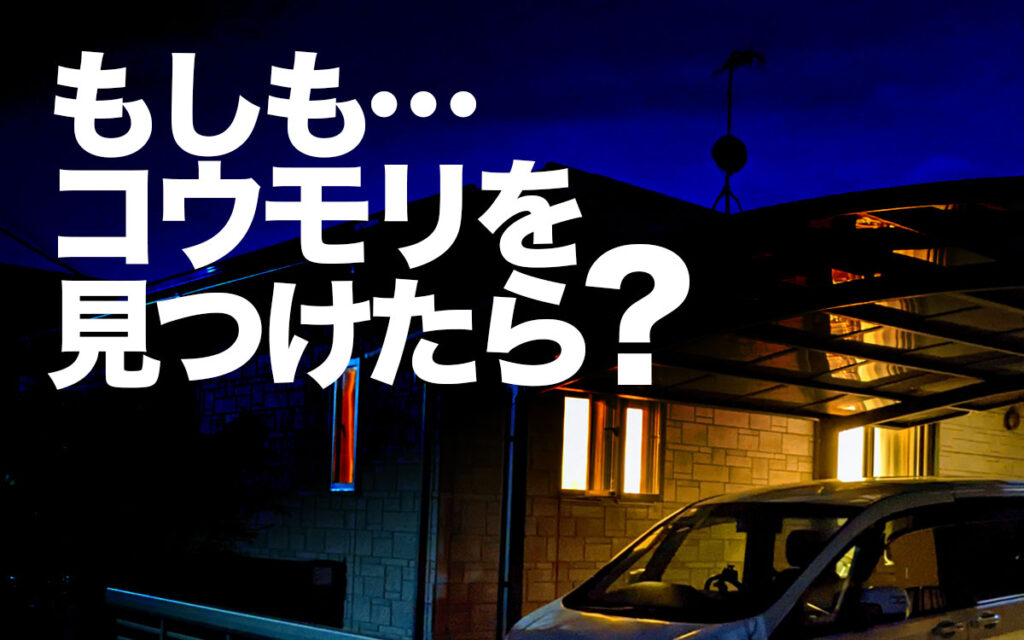
家の外壁や駐車場、あるいは室内の屋根裏や換気口でコウモリを見つけたり、フンが落ちていた場合、どう対応すればよいのでしょうか?
結論:素手で触ったり自力で駆除しようとするのは危険です。感染リスクや法的規制もあるため、清掃や対策は専門業者に任せるのが安全です。
掃除や素手はNG?吸い込むのが最も危険!
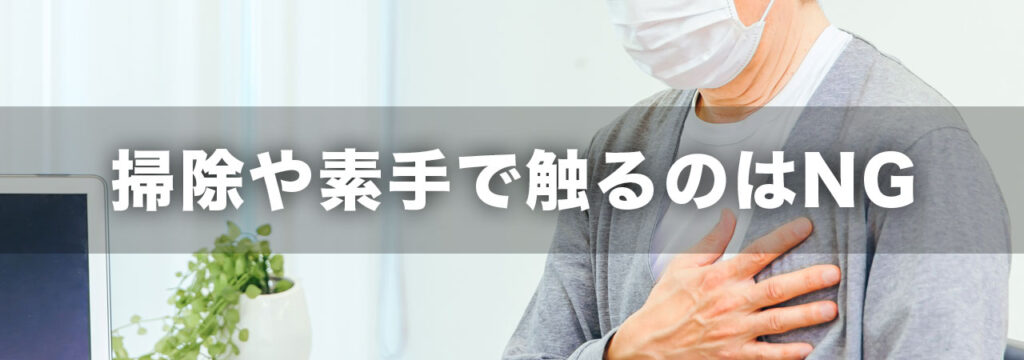
乾燥したコウモリのフンは崩れやすく、舞い上がった粉状のフンやカビの胞子を吸い込むと、ヒストプラズマ症などの呼吸器感染につながるおそれがあります。
また、フンや尿には細菌や寄生虫も含まれていることがあり、素手で触れるのは絶対に避けてください。
消毒・侵入口の封鎖・清掃はプロに任せる

コウモリのフンが落ちていた場所の清掃は、防護具や適切な消毒処理が必ず必要です。
また、実際にコウモリが付近に潜んでいないかどうかの調査や、侵入口を見つけて封鎖する作業にも専門的な知識が求められるため、自己判断での作業はおすすめできません。
不安を感じたら、市区町村や保健所、専門の防除業者に相談するのが確実です。
コウモリ駆除には鳥獣保護管理法も関係

日本に生息するコウモリは、「鳥獣保護管理法」によって保護されています。
許可なく捕獲や殺傷を行うと法律違反になるおそれがあるため、駆除や追い出しを行う場合は、自治体の指導や専門業者の対応が必要です。
コウモリの鳥獣保護管理法はなぜ?
コウモリは農業害虫や不快害虫を食べて数をコントロールしたり、果樹の花粉を運ぶなど、自然界で重要な役割を担っているため、「鳥獣保護管理法」で保護対象になっていますが、人の住環境に入り込んだ場合は、健康被害や未知のウイルス保持など、見逃せない衛生リスクもあり注意が必要です。
よくある質問
- コウモリに触ってしまいました。大丈夫でしょうか?
- 結論:素手で触った場合はすぐに手を洗い、消毒しましょう。
特に、コウモリのフンや体に付着したカビの胞子を吸い込むと、ヒストプラズマ症などの呼吸器感染のリスクがあるとされています。また、海外では狂犬病ウイルスを持つコウモリも確認されていますが、日本の野生コウモリからは今のところ発見されていません。ただし、体にはダニや細菌などの病原体が付着している可能性もあるため、噛まれた場合や、傷口に触れた・目や口をこすった場合は、念のため医療機関に相談しましょう。 - コウモリのせいで空気感染することはありますか?
- 結論:ウイルスのような「人から人へうつる空気感染」は基本的にありません。
ですが、ヒストプラズマ症はコウモリのフンに含まれるカビの胞子(ヒストプラズマ)を吸い込むことで発症することがあり、フンが乾燥して粉状になり、空気中に広がることが原因とされています。特に免疫力が弱い方や乳幼児・高齢者は、呼吸器への影響が出やすくなるため、コウモリのフンが見つかった場合は注意が必要です。 - コウモリの病原菌は何が危険?
- 結論:コウモリの病原菌としては、体やフンに付着したカビや細菌に加えて、寄生虫も危険といえます。コウモリのフンからは、ヒストプラズマやクリプトコックスなどの病原体が検出されており、空気中に舞って吸い込むことで呼吸器に影響を及ぼす可能性があります。また、アブラコウモリには吸血性のダニやトコジラミが寄生していることもあり、室内に拡散すると皮膚炎やアレルギーの原因になるおそれがあります。直接触れたり吸い込まなければリスクは高くありませんが、見つけた場合は放置せず、専門業者に相談するのが安全です。
まとめ
- コウモリが「汚い」とされる理由は、糞尿の汚染・悪臭・カビ・ダニ・トコジラミなど衛生被害が多岐にわたるためです。
- コウモリから病気が空気感染する可能性は低いですが、粉状のフンやカビを吸い込むことで呼吸器系への影響が懸念されます。
- 「コウモリ菌」という医学用語はありませんが、糞尿や寄生虫を介して健康被害につながる病原体は存在します。
- コウモリに注意が必要な方は、高齢者だけでなく、妊婦・乳幼児・免疫力が弱い方・アレルギー体質の方は特に注意が必要です。
- 屋外で見かけても触らず、住宅内や周辺で見つけた場合は、保健所や専門業者に相談するのが安全です。
「コウモリ」と聞くと、吸血や恐ろしいウイルスを想像される方もいるかもしれません。ですが、家に住み着く「アブラコウモリ」は血を吸うことはなく、日本国内では狂犬病などの感染例も現在報告されていません。
とはいえ、フンに含まれるカビや細菌、体に寄生しているダニ・トコジラミなど、連鎖して気が付きにくい衛生リスクが存在することは確かです。
お困りの際は、鳥獣保護法などの法律に則った安全な方法で対応いたしますので、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。
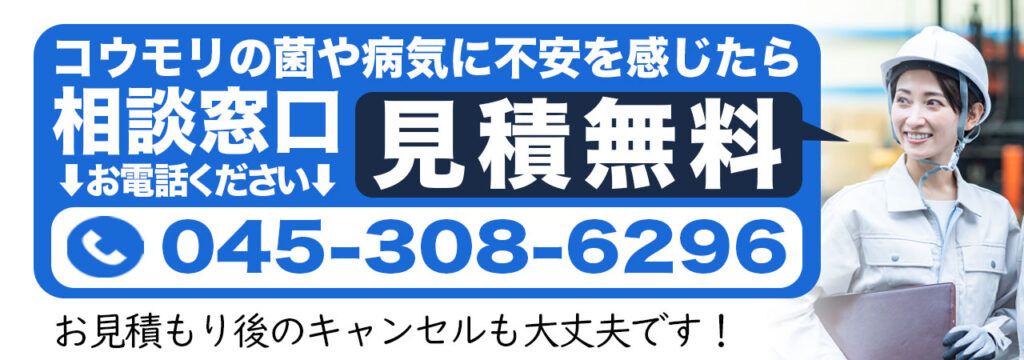

監修:引田 徹【クリーン計画プロープル株式会社:施工部長】
取材担当:フジテレビ「ライブニュースイット」|BS-TBS「噂の!東京マガジン」|テレビ朝日「スーパーJチャンネル」|日本テレビ「news every.」|テレビ朝日「報道ステーション」|フジテレビ「めざまし8」|テレビ朝日「グッド!モーニング」|テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」|日本テレビ「DayDay.」|TBSテレビ「THE TIME,」|そのほか多数メディア出演対応(順不同)
資格:(公社)日本ペストコントロール協会|(公社)神奈川県ぺストコントロール協会|(一社)日本有害生物対策協会|日本ペストロジー学会|(公財)文化財虫菌害研究所|しろあり防除施工士|建築物ねずみ昆虫等防除業登録|(一社)日本鳥獣被害対策協会|セントリコン・テクニカル・マスターなどその他にも多数の資格を保有
<参考文献>:大沢 啓子, 大沢 夕志, 家屋・建物内をねぐらにするコウモリ, 都市有害生物管理, 2016, 6 巻, 2 号, p. 91-95, 公開日 2020/02/22, Online ISSN 2435-015X, Print ISSN 2186-1498, https://www.jstage.jst.go.jp/article/urbanpest/6/2/6_91/_article/-char/ja/
<参考文献>:日髙 敏隆、日本動物大百科 1、平凡社、1996、p.156、
<参考文献>:船越 公威、コウモリ学: 適応と進化、東京大学出版会、2020、p.299、